
「どうしてうちの子、何度言っても言うこと聞かないの?」
「つい怒ってしまって、あとで自己嫌悪…」
そんな毎日に、心がすり減っていませんか?
私も同じでした。
でも、アドラー心理学に出会ってから、「子どもの行動の見方」が少しずつ変わり、イライラも減って、親子の時間があたたかいものに変わっていったんです。
この記事では、アドラー心理学がなぜ子育てに向いているのか?
そして、我が家で実際に感じた3つの変化と、すぐに試せる声かけや考え方をお伝えします。
子どもともっと仲良くなりたいママへ。
今日から始められる“心が楽になる子育て”のヒント、受け取ってみませんか?
アドラー心理学とは?

アドラー心理学とは、ウィーン生まれの医師、アルフレッド・アドラーが提唱した心理学です。
過去よりも「これからどう生きるか」に注目する、前向きな考え方が特徴です。
第一次世界大戦を経て、アドラーはこう考えました。
「二度と戦争が起こらないためには、人間の心を育て直さなければならない」
その思いから、子どもの育ちや教育に目を向け、母親や教師へのカウンセリングにも力を注ぎました。
アドラー心理学が伝えているのは、「上から支配する子育て」ではなく、子どもと「よこの関係」で信頼し合うことの大切さ。
怒ったり褒めたりしてコントロールするのではなく、
子どもを一人の人として尊重し、勇気を持って生きられるようにサポートする。
そんな関わり方ができる子どもたちが育てば、社会ももっと優しく、平和になる
アドラーはそう考えていました。
子育てに向いている3つの理由

「叱らない・褒めない」で育つ“自己教育力”
子どもは、生まれながらに「自分の力で育とうとする力(=自己教育力)」を持っています。
だから、アドラー心理学では叱らない・褒めないという関わり方を重視します。
なぜなら、叱る・褒めるには次のようなリスクがあるからです。
- 叱られたり褒められないと、やる気が出ない
- 失敗を恐れてチャレンジできなくなる
- 自信をなくしてしまう
- 指示がないと動けない「指示待ち人間」になる
また、「ご褒美」や「罰」も同じ。
これらは「外からの刺激(外発的動機づけ)」なので、言ってくれる人がいなければ子どもはやらなくなってしまいます。

だからこそ、
「自分で考え、自分で選び、動ける子に育ってほしい」
そんな願いを持つご家庭に、アドラー心理学はぴったりなんです。
「行動の目的」に注目してイライラ減少
子どもが困った行動をしたとき、ついこんなふうに思っていませんか?

「私の育て方が悪かったのかも…」
「もっと愛情をかけてあげればよかったのかも…」
でも、アドラー心理学では「すべての行動には目的がある」と考えます。
子どもは困らせたくて困らせているのではなく、
「見てほしい」「かまってほしい」というサインとして行動しているのです。
たとえば:
- わざとイタズラをする
- グズグズして動かない
- 兄弟を叩いてしまう
これらは「注目されたい」「関わってほしい」という気持ちの現れです。
この気持ちに気づかず叱ってしまうと、
子どもは「困ったことをすると見てもらえるんだ」と学習してしまいます。
「この子、今どんな気持ちなんだろう?」と想像するだけで、
イライラが共感に変わり、親子関係がグッとあたたかくなるはずです。
「勇気づけ」であたたかい親子の関係をつくる
アドラー心理学では、「勇気づけ」がとても大切です。
勇気づけとは、できているところや努力している姿に注目し、その子の“内側”から力を引き出す関わり方のことです。
叱ったり褒めたりではなく、
「あなたは価値があるよ」「ちゃんと見てるよ」と伝える声かけです。

この関わり方ができるようになると、
子どもは安心してチャレンジできるようになり、親もイライラがぐんと減ります。
勇気づけが習慣化すると、子どもはこう育つ
そして、“勇気づけ”が日常に根づくと、子どもはこんなふうに育っていきます。
- 「ここを乗り越えれば、もっと成長できる!」と、人生のリスクや困難にチャレンジできるようになる
- 「困難は克服できるものだ」と、前向きに捉えられるようになる
- 目標に向かって、自分だけでなく仲間と協力したり、誰かの役に立つ喜びを感じられるようになる
こうした「生きる力」は、一朝一夕では育ちません。
でも、日々の小さな声かけやまなざしの積み重ねが、確実に子どもの土台を育てていくのです。
具体的な声かけ例(共感・感謝・プロセスに注目)
勇気づけの声かけには、以下のような言葉が効果的です:
- 「〇〇くんの今回の結果、ママも本当にうれしい!」
→【一緒に喜ぶ】ことで、子どもと心がつながります - 「〇〇くんが手伝ってくれて助かったよ!」
→【感謝】を伝えると、自分の行動に意味を感じられます - 「この部分、ずっと頑張ってきたところだもんね」
→【プロセス】を認めることで、結果だけにとらわれなくなります - 「〇〇くんがいてくれて幸せだなぁ。ありがとう」
→【存在そのもの】に感謝されることで、子どもは「愛されている」と実感できます
これらは、言葉だけでなく、態度・表情・声のトーンもとても大切。
「伝えよう」と思う気持ちがあってこそ、子どもの心にまっすぐ届きます。
我が家で起きた3つの変化(実例)

アドラー心理学を取り入れてみたら、
「子どもの行動」が変わっただけでなく、私自身の“声のかけ方”や“見方”が変わりました。
その結果、親子の関係も少しずつあたたかくなっていったのです。
ここでは、私の実体験を3つご紹介します。
1、片付けの声かけを変えたら…
わが家の子どもたちは、片付けがちょっと苦手。
ついつい私も

「ちゃんと片付けて!」「なんでできないの?」
とガミガミ言ってしまい、
お互いストレスを感じる日々でした。
そこで、試しにアドラー心理学で学んだ“勇気づけ”をやってみることに。
子どもが片付けたおもちゃを指さして、

「おもちゃ、片付けられたね」
と声をかけてみました。
すると、「うん!」ととっても嬉しそうな笑顔。
そしてまた別のおもちゃを持ってきて、

「これも片付けたよ〜!」
と自分から行動する姿を見ることができました!!

「怒らなくても、ちゃんと伝わるんだ」と思えた出来事でした。
2、挑戦でつまずいたときのフォロー
ある日、長男が「くもんのくみくみスロープ」で黙々と遊んでいました。
でも、どうしても一か所だけパーツがうまくはまらず、イライラ…。

「これ、はめたいんだけど!!!」
と感情が爆発しそうに。
そこで私は、すかさずこう声をかけました。

「ここまでひとりで組み立てたの、すごいね!」
「前はひとりじゃできなかったのに、成長したね!」
すると、表情が落ち着いて、

「ママ、手伝って」
と素直に言ってくれました。
一緒に組み立てを完成させた後は、笑顔でビー玉を転がして遊べたんです。

子どもがイライラしているときこそ、できていることに注目する大切さを学びました。
3、自分で動けるようになるまで待ってみた話
長男は、幼稚園から帰ってきても水筒を玄関に置きっぱなしにしがち。
私は毎日「水筒は?」と声をかけていましたが、ある日こんな反応が返ってきました。

「うん!わかってるけど!!!」(と、イライラ)
私の中で「このままじゃ“うるさいお母さん”になっちゃう⋯」という危機感が。
そこで思い切って「子どもを信じて待つ」ことにしました。
注意するのをやめ、小さなできたことだけに注目。
数日後、ふとキッチンを見ると、
キッチン台の上に水筒が置いてあったのです!
すかさず

「水筒ありがとう!持ってきてくれたんだね!」
と声をかけると、得意げな表情の長男。
弟も、長男の姿を見て自然と行動する回数が増えました。

「待つ」ことの勇気、そして“信じる”という関わり方の力を、私はこの出来事から教わりました。
それでもイライラしてしまう時のヒント

「課題の分離」という考え方
たとえば、子どもが宿題をやらないとき。
「やりなさい!」と叱りたくなるけれど、
それは“子どもの課題”であって、“親の課題”ではないというのがアドラー心理学の視点です。
子どもが宿題をやらないことで困るのは子ども自身。
だから、それを「やらせる」のではなく、「選ばせる」姿勢が大切です。
アドラーはこう言います。
「あらゆる人間関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むことで起きる」
「この行動の結果を引き受けるのは誰か?」を考えると、
誰の課題かが見えてきます。
つい口を出してしまいそうな時は「まぁ、いっか」
私もまだまだ修行中の身。
ついイラっとしたとき、思わず言いそうになることがあります。
そんなときの魔法の言葉は、

「まぁ、いっか」
です。
私たち親も、完璧じゃなくていい。
余裕がない日もあるし、気持ちが疲れてる日もある。
そんな自分にも「勇気づけ」を忘れずに。
できることから、少しずつで大丈夫です。
まとめ

アドラー心理学は、「子どもをどう変えるか」ではなく、「親の見方をどう変えるか」を教えてくれます。
- 叱らない・褒めない
- 行動の目的を見る
- 勇気づけを意識する
- 信じて待つ
- 課題を分ける
どれも、今日から始められる小さなことばかり。
でもその積み重ねが、親子の関係をじんわり変えてくれるんです。
「怒らない子育てをしたい」
「もっと子どもと信頼し合える関係を築きたい」
そう思っているあなたに、アドラー心理学の考え方が届いたらうれしいです。
子育ての正解は一つじゃない。
でも「子どもと一緒に育ち合う道」は、きっとここにあります。
📕私がアドラー心理学の子育てに出会えたのは、こちらの2冊です。
どちらも「子どもを怒らずに育てたい」と思っていた私に、あたたかい視点をくれました。
テーマごとに「マンガ→解説」の順で書かれているので読みやすく、明日からすぐに実践できるヒントが詰まっています。
※Amazonリンクは後日追加予定です。
📘もっと深くアドラーの思想を学びたい方へ
「アドラー心理学の本質を、対話形式でじっくり学びたい」という方には、こちらもおすすめです。
◎人間関係や親自身の生き方に悩む方にぴったりの一冊です。
※Amazonリンクは後日追加予定です。
💡もっと子どもと向き合いたいと思ったあなたへ
📕 子どもの心をそっと育ててくれる絵本
寝る前や一緒に過ごすひとときに、絵本が“心のかけ橋”になってくれました。
→※絵本ナビでおすすめの絵本を探せるようリンクを貼る予定です。
🧸 「怒らない」を助けてくれた、仕組みとアイテム
ついイライラしてしまうときも、“環境を整える”ことでラクになることがありました。
わが家で役立ったものをこれから少しずつ紹介していきます。
以上、ふるちゃんでした。
今日も一日おつかれさまでした!💮

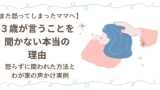

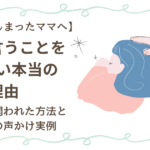
コメント