
「失敗しても、また挑戦できる子になってほしい。」
そう願いながらも、うまくいかないとすぐに諦めてしまったり、ちょっとしたことで気持ちが折れてしまったり⋯。
子どもの“打たれ弱さ”に不安を感じたことはありませんか?
私自身、子どもの将来を思ったとき、「レジリエンス=折れない心」は、生きていく上で何より大切な力だと感じました。
この言葉と出会ったのは、絵本『きみのこころをつよくするえほん』がきっかけです。
読み進めるうちに

「これだ。これがあれば、どんな人生もきっと前に進める。」
と確信しました。
この記事では、絵本から学んだ“レジリエンス”の本質と、それを育むために日々の子育てでできる声かけ・関わり方をご紹介します。
私が実践して感じたことや、子どもに現れた変化もあわせてお伝えするので、きっとヒントが見つかるはずです。
失敗を責めるのではなく、「またやってみよう!」と言える子に育てるために。
そして、何があっても自分の人生を楽しめる心の土台を育てるために。
今、親としてできることを一緒に考えてみませんか?
レジリエンスってなに?〜子どもの「折れない心」〜

子どもの「折れない心」って、どんな心のことだと思いますか?
私は、「失敗してもやってみる」「自分の気持ちと向き合って、立ち直る力」だと感じています。
これがまさに「レジリエンス(resilience)」と呼ばれる力です。
レジリエンスという言葉を、私は絵本『きみのこころをつよくするえほん』を通して知りました。
その中で監修の足立啓美さんは、こんなふうに語っています。
「この心の力を幼少期に育てることで、心の健康、対人関係、学業に良い影響があることがわかっています。」
「レジリエンスは、経験を通して育つ力です。特に幼少期において最も重要になるのが、自分の感情に上手に対応できる力、欲求不満に耐える力を育てることです。」出典:きみのこころをつよくするえほん
大人でも「怒り」や「悔しさ」に飲み込まれそうになることがありますよね。
それを乗り越えていける力を、小さなうちから少しずつ育てていく。
それこそが、レジリエンスを育てる第一歩だと実感しました。
レジリエンスの高い子の特徴

レジリエンスは、特別な子どもだけが持っているものではなく、後天的に育てていける「心の力」です。
では、レジリエンスが高い子どもには、どんな特徴があるのでしょうか?
実際に見られる様子をいくつかご紹介します。
失敗しても立ち直りが早い
失敗やうまくいかないことがあっても、「じゃあ次どうしようかな?」と前を向くことができます。
気持ちの切り替えが早いので、落ち込みすぎず、次の一歩を踏み出すことができるのです。
自分の気持ちを言葉で表現できる
イライラ・悲しい・くやしい。
そんな気持ちを、少しずつでも言葉にできることも、レジリエンスの高い子の特徴のひとつ。
気持ちを表現できることで、感情の爆発を防ぎ、人との関わりもスムーズになります。
困ったときに、誰かに助けを求められる
「ひとりで頑張らなきゃ」ではなく、「困ったら誰かに頼ってもいい」と思えていることも大切な力です。
これは、自分に安心感があるからこそできる行動なんですね。
チャレンジすることを恐れない
失敗を「悪いこと」と思っていないため、新しいことにも積極的です。
「やってみたい!」「また挑戦してみよう!」という前向きな気持ちが自然と育まれています。
もちろん、これらの特徴が全部そろっていなくても大丈夫。
レジリエンスは、日々の声かけや関わり方の中で少しずつ育っていくものです。
次の見出しでは、親としてどんな関わりができるのかを紹介します。
レジリエンスを育てる3つの声かけ&関わり方


「どうしてできなかったの?」
「さっき言ったでしょ?」
そんなふうに、つい責めるような言い方をしてしまったこと、ありませんか?
私はあります。
でも、そんな対応をしてしまうと、子どもは「失敗=怒られること」と思い込み、新しい挑戦に対して臆病になってしまいます。
だからこそ、私は声かけを見直しました。
レジリエンスは、日々の親子の関わりの中で少しずつ育っていくもの。
わが家で実践して効果を感じた「3つの声かけ&関わり方」をご紹介します。
【1】失敗を責めず、「次はどうしようか?」と前を向く
失敗したとき、つい

「またやったの?」
「どうしてそうなるの?」
と言いたくなることも。
でも今は、

「失敗してよかったね」
「この失敗から何がわかった?」
「次はどうすればうまくいくかな?」
と前向きな声かけを心がけています。
あるとき、長男が挑戦してうまくいかなかった後にこう言いました。

「ぼく、なんでもやってみる!がんばる!」
それを聞いたとき、本当にうれしかったのを覚えています。
以前の彼は、

「できない。」
「やらない。」
と言っていたのに、考え方が少しずつ変わってきたのです。
子どもが失敗したときの声かけひとつで、「またやってみよう」と思えるか、「もうやりたくない」と思うかが決まる。
それくらい、親の対応には大きな力があると感じています。
【2】感情を言葉にする練習を一緒にする
レジリエンスを育てるうえで、土台になるのは「安心感」です。
悔しかったり悲しかったりする気持ちに共感し、受け止めてあげましょう。
「怒ってるんだね」「悔しかったんだね」など、子どもの気持ちに言葉を当ててあげることで、感情を自覚しやすくなります。
そうすると、自分の気持ちを整理する力(自己理解力)も少しずつ育っていきます。
また、「ちゃんとわかってくれる人がいる」という安心感が、立ち直る力=レジリエンスの源になるのです。
【3】「あなたならできる」と信じて見守る
子どもが挑戦する時、失敗しそうで口を出したくなることもありますよね。
でも、“うまくいかない時にこそ、信じて見守る”ことが子どもの自信に繋がります。

「最初からうまくいく人なんていないよ」
「失敗しても、ママは応援してるよ」
「きっとできる。やってごらん」
そんなふうに、親の安心感や信頼を伝えていくことで、「自分なら大丈夫」と思える内側からの強さが育っていくのだと感じています。
レジリエンスは、1日で身につくものではありません。
でも、親の関わりひとつで、失敗を恐れず前向きに進んでいく子になっていける。
私自身、子どもとの関わりの中で、そう確信するようになりました。
大人がレジリエンスを学ぶとどうなる?


「レジリエンスを育てるのは子どもだけじゃない。大人の私にこそ必要だったんだ。」
レジリエンスの考え方に出会ったとき、私はそんなふうに感じました。
感情をコントロールする力、いわゆる「アンガーマネジメント」は、実は私が長年、苦手としてきたものでもあります。
子どもの頃からそうしたスキルを学んでこなかった私は、大人になってから何度も苦労してきました。
でも、意識して練習を重ねることで、今ではイライラしても反射的に怒るのではなく、

「私は今、怒っているな。」
と一歩引いて見つめることができるようになってきました。
たとえば、子どもが癇癪を起こしたとき。
以前の私は、感情的にぶつかってしまうことがありました。
けれど今は、冷静に

「どうしてこんな気持ちになったのかな?」
と問いかけ、 落ち着いて対応できることが増えてきたのです。
これは、子育てのストレスを軽くするだけでなく、「こんな風に感情と付き合えばいいんだ」というお手本を子どもに見せることにもつながっています。
自分自身が感情と向き合う力をつけていくことで、「子どもにもこの力を伝えたい。」「いい連鎖を後世につなげたい。」という気持ちが自然と湧いてくる。
レジリエンスは、子どもだけでなく、親である私自身の人生も豊かにしてくれると、そう実感しています。
まとめ「失敗しても大丈夫」と伝え続けよう

レジリエンスは、失敗しても立ち上がる“心のしなやかさ”。
それは、一度教えたからといってすぐに身につくものではなく、日々の積み重ねと、あたたかい関わりの中で少しずつ育っていく力です。

「失敗しても大丈夫だよ」
「うまくいかなかったけど、挑戦したことがすごいね」
そんな小さな声かけの一つひとつが、子どもの心を強く育てる土台になっていきます。
完璧な対応ができなくても大丈夫。
親だって、毎日が試行錯誤です。
でも、「どうしたらこの子の力になるか」と考えるあなたの気持ちが、すでに子どもにとっての一番の支えです。
一緒に転びながら、何度でも立ち上がる姿を見せていきましょう。
それがきっと、子どもが将来自分の力で歩いていける大きな自信につながります。
子育てに関わる全ての人と子ども達の笑顔がもっと増えますように。
以上、ふるちゃんでした。
今日も本当におつかれさまでした!
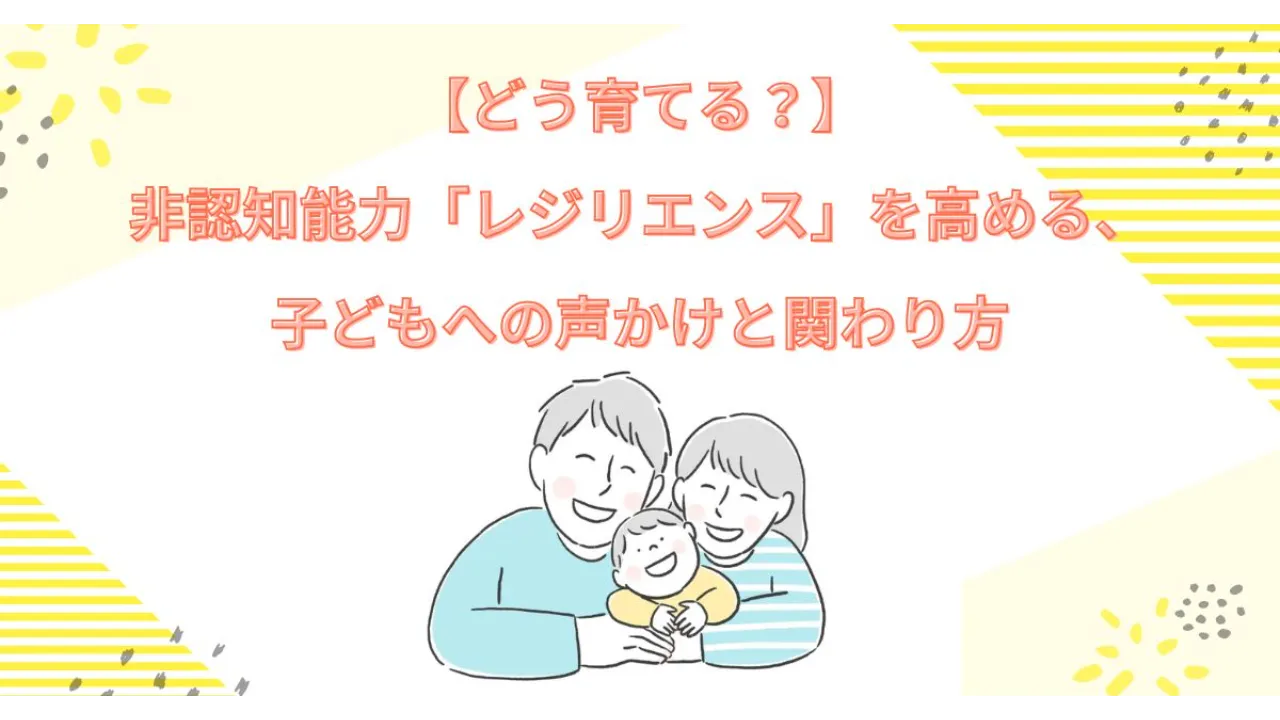
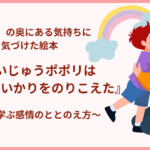

コメント